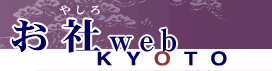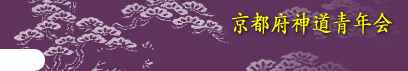節分とは、季節の変わる節目の意味で、本来は立春、立夏、立秋、立冬の前日をさしますが、今日では冬から春に移る立春の前日のみをさし、旧暦では元旦から7日までの間にあたります。また古くより宮中において行われていた追儺(ついな、疫鬼を追払う行事)行事が、立春をもって年が改まるという考え方から、節分の日に行われるようになったといわれています。現在の節分行事(豆撒き行事等)は室町時代に一般化したといわれ、鬼と神主の問答の後、言い負かされた鬼が退散する時に年男が、『鬼は外、福は内』と勇ましい声を出して豆撒きの鬼ヤライをする形が一般的となっています。
このような節分祭は、冬の間の暗い気分を一掃し、希望に満ちた新春を迎えようとの日本人の除災招福の願いがこめられているのです。 |