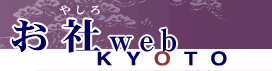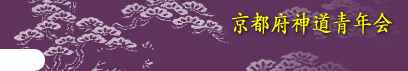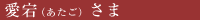 |
| 京都市右京区の愛宕山山頂に鎮まる愛宕神社が総本社で、御祭神は本宮(稚産日命わかむすびのみこと他四柱)と若宮(雷神他二柱)。この神様をまつった社は多く、全国的に防火の守護神として信仰されています。 |
| pagetop▲ |
 |
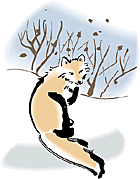 稲荷神社の数は全国に約3万社あり、日本の神社総数の3分の1近くを占め最も広く信仰されていることがわかります。 稲荷神社の数は全国に約3万社あり、日本の神社総数の3分の1近くを占め最も広く信仰されていることがわかります。
その総本社は京都の伏見稲荷大社で主祭神は宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)、和銅4年(711年)2月7日初午の日に御鎮座と伝えます。
「イナリ」の語源は「稲生り」つまり五穀豊穣の意味です。
狐は、お稲荷さんの神使とされています。 |
| pagetop▲ |
 |
| 西宮市の西宮神社、島根県の美保神社を総本社とします。御祭神は、事代主神(ことしろぬしのかみ)または蛭子神(ひるこのかみ)をまつります。「えびす」には古く「夷」「戎」の字があてられ、海のかなたからやって来て幸いをもたらす漁村に発した信仰が次第に内陸に伝播し、農業神、さらに商工業繁栄の神ともなり福神として正月の十日えびすには多くの人がお参りします。 |
| pagetop▲ |
 |
お諏訪さまの総本社は、長野県の諏訪湖の近くに鎮座する諏訪神社で、長野・新潟の両県を中心に全国に約5千社分布しています。
御祭神は、建御名方神(たけみなかたのかみ)を主祭神とし、この神名の「タケ」は霊威の強いことを表す敬称で、「ミナカタ」は「水潟」に通じる水辺を意味し、霊威が強い水辺の神を意味します。
つまり、水を司どり我々に限りなく恵みをくださる水と農耕の神さまとして広く信仰されています。 |
| pagetop▲ |
 |
全国に約300社程あり、京都の鞍馬山の谷間にある貴船神社を総本社とします。
祭神は、高 神(たかおかみのかみ)、闇 神(たかおかみのかみ)、闇 神(くらおかみのかみ)などで、往古、多くは貴布禰神社と記し雨乞い(反対に止雨乞い)、水乞いの神として広く信仰されています。 神(くらおかみのかみ)などで、往古、多くは貴布禰神社と記し雨乞い(反対に止雨乞い)、水乞いの神として広く信仰されています。 |
| pagetop▲ |
 |
「こんぴら船々、追手に帆かけてシュラシュシュシュ」の民謡は、盛んな金毘羅詣りにともなって全国津々浦々に流行したもので、その本社は香川県琴平町の金刀比羅宮で、御祭神は大物主神(おおものぬしのかみ)です。
航海や漁業にたずさわる人々の信仰を集め、江戸時代に入り瀬戸内海を通る大阪商人の船乗りを通じ、信仰は庶民の間にも広まり、伊勢のおかげ参りとともにこんぴら参りは船乗りにとって、一生に一度は行きたいものでした。 |
| pagetop▲ |
 |
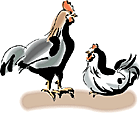 全国には1万8000社の神明社(神明宮・神明神社)がありますが、そのほとんどは天照大御神をおまつりし、伊勢信仰がさかんになるにつれて、伊勢神宮の御祭神が各地におまつりされました。 全国には1万8000社の神明社(神明宮・神明神社)がありますが、そのほとんどは天照大御神をおまつりし、伊勢信仰がさかんになるにつれて、伊勢神宮の御祭神が各地におまつりされました。
三重県伊勢市にある伊勢の神宮は、天照大御神をおまつりする皇大神宮(内宮)と豊受大御神をまつる豊受大神宮(外宮)との総称で全国の神社根本社と仰がれ、「本宗(ほんそう)」と呼ばれています。また鶏を神鶏として大切にしています。 |
| pagetop▲ |
 |
| 住吉神社は底筒男命(そこつつおのみこと)、中筒男命(なかつつおのみこと)、表筒男命(うわつつおのみこと)の三神をまつる神社で、神功皇后が三韓征伐をしたときこの三神を祓の神として、又同時に海の神、水の神としてまつり、遠征帰途に福岡県・山口県・大阪府にそれぞれ住吉神社を創建されました。 |
| pagetop▲ |
 |
 天神さまと呼ばれる神社は全国に1万500社あり、御祭神は菅原道真公。学問の神様として知られる道真公は平安時代初期の人で、学問の名家に生まれ、すぐれた才能を示し、右大臣として立身出世をした人で、その出世をねたんだ藤原氏の画策により九州の太宰府に左遷され亡くなります。死後、道真公の墓所に建てられたのが太宰府天満宮で、神霊を京都におまつりしたのが北野天満宮であり道真公をお祀りした神社の宗祀です。 天神さまと呼ばれる神社は全国に1万500社あり、御祭神は菅原道真公。学問の神様として知られる道真公は平安時代初期の人で、学問の名家に生まれ、すぐれた才能を示し、右大臣として立身出世をした人で、その出世をねたんだ藤原氏の画策により九州の太宰府に左遷され亡くなります。死後、道真公の墓所に建てられたのが太宰府天満宮で、神霊を京都におまつりしたのが北野天満宮であり道真公をお祀りした神社の宗祀です。
牛は、天神さまゆかりの動物で、境内にその像を見かけることがあります。 |
| pagetop▲ |
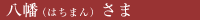 |
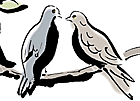 全国に約2万5千社あり、御祭神は普通応神天皇(おうじんてんのう)、比売大神(ひめおおかみ)、神功皇后(じんぐうこうごう)の三神です。 全国に約2万5千社あり、御祭神は普通応神天皇(おうじんてんのう)、比売大神(ひめおおかみ)、神功皇后(じんぐうこうごう)の三神です。
八幡信仰の発祥は大分県の宇佐神宮(宇佐八幡宮)で、京都の石清水八幡宮とともに、八幡社の総本社と仰がれ広く全国にまつられるようになりました。八幡さまは皇室の崇敬する神様であるばかりではなく、源氏一族をはじめ武人の神として崇敬を集め又広く地域の民衆の神様としても信仰されるようになりました。
鳩は八幡さまの神使とされています。 |
| pagetop▲ |
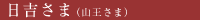 |
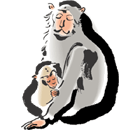 日吉神社は山王社とも呼ばれ、滋賀県大津市にある日吉大社が総本社で、大山咋神(おおやまくいのかみ)を主祭神としてまつります。 日吉神社は山王社とも呼ばれ、滋賀県大津市にある日吉大社が総本社で、大山咋神(おおやまくいのかみ)を主祭神としてまつります。
大山咋神は日枝山(比叡山)の山の神、地主の神で延暦寺からは山王権現と称され、神仏習合の形をとり、大きな発展をとげました。
猿は日吉さまの神使とされています。 |
| pagetop▲ |
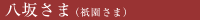 |
八坂さま(祇園さま)は京都の八坂神社を本社として西日本に多く、御祭神は、須佐之男命(素戔嗚尊 すさのおのみこと)を主祭神とします。
9世紀中期より京都では疫病が流行し、その原因は怨霊と考えられ、その霊を鎮めるために御霊会が行われ、八坂社は牛頭天王、須佐之男命という疫病除けの神をまつっていることから、祇園御霊会がたびたび行われ、八坂社の御神徳が広まりました。 |
| pagetop▲ |
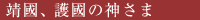 |
靖國神社は、明治2年に建てられた東京招魂社(しょうこんしゃ)が前身で、同12年に靖國神社と改称されました。
御祭神は、明治維新の殉難(じゅんなん)者、諸事変、戦没において国に生命をささげた人々の英霊240余万柱をまつります。
各府県には護國神社があり、前身は各地の招魂社でその府県出身の護國の英霊をおまつりしています。 |
| pagetop▲ |
|