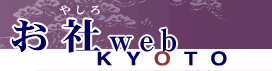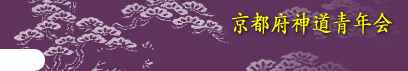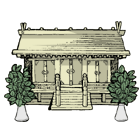 神社の御札を納める神棚は、家のなかでもなるべく清らかな、しかも家族の近づきやすいところがよく、その意味で食事をする部屋なども適当です。なるべく南向き、または東向きにおまつりすることです。二階のある家では、なるべく人の踏む場所の下にならないように心がけます。高さは、一段高い所が良いのですが、あまり高すぎて、掃除やお供えの出来ない所も困ります。 神社の御札を納める神棚は、家のなかでもなるべく清らかな、しかも家族の近づきやすいところがよく、その意味で食事をする部屋なども適当です。なるべく南向き、または東向きにおまつりすることです。二階のある家では、なるべく人の踏む場所の下にならないように心がけます。高さは、一段高い所が良いのですが、あまり高すぎて、掃除やお供えの出来ない所も困ります。
お供物は、丁重にすれば際限のないものですが、最も簡単な場合は、中央に洗米又はご飯、向かって右に塩、左に水の三品を供えます。これは人間の食物として一日も欠くことのできないものですから、神饌の中心となります。その他にも酒・餅・魚類・海草類・野菜などをお供えします。 |